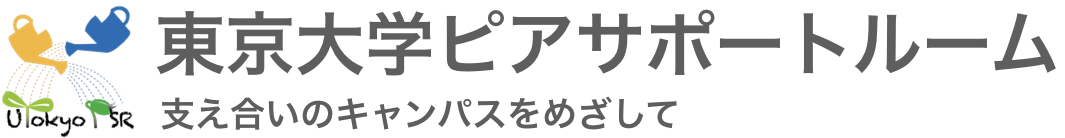総合窓口ってどんなところ?
総合窓口は相談支援研究開発センターにある相談窓口のひとつで、学生や教職員、保護者などからあらゆる相談を受け付けています。相談機関ガイドの企画では以前「なんでも相談コーナー」にインタビューを行いましたが、装い新たに「総合窓口」となったことで、新たにインタビューを実施させていただきました。どのような点が変わったのでしょうか。
※旧・なんでも相談コーナーの記事はこちら
場所:本郷キャンパス、プレハブ研究A棟1階(地図)
開室日時:月曜日~金曜日、10:00~16:00
※利用にあたってはHPをご確認ください。
——まず基本的なこととして、学生が総合窓口でできることを簡単に教えてください。
総合窓口には、精神科医と臨床心理士、公認心理師、精神保健福祉士、ベテラン職員が常駐しています。専門家がいるので、医療的な見方や心理的な見方、福祉的な見方で、学生の様々な悩みに応えられます。それに加えて英語と中国語にも対応しています。
——学生相談所などの他の相談機関と相談窓口ではどのような対応の違いがありますか。特定の悩みがあったとき、どちらに行けば良いですか。
迷ったときには、総合窓口を利用してください。学生相談所との違いとして、総合窓口では、例外もありますが基本的に継続面談をおこなっていない点があり、相談内容に応じて連携している他の相談機関を紹介することになります。
申し込みはウェブサイトのリンクからされる方が多いです。電話の場合は、その場で対応して解決することもあります。「いつでもZoom」(火・木曜日の13:00〜15:00に開室)という予約不要の相談も受け付けていますが、こちらは職員が対応しています。1人あたり20分程度で、必要な場合は専門家が入ることもあります。
——なぜ「なんでも相談コーナー」から「総合窓口」へと名前を改めたのですか。また、それにあたってどのような点が変わったのですか。
「なんでも相談コーナー」のころは大学職員が相談を受けていましたが、3年前に精神科医と心理士が常駐するようになり、「総合窓口」となりました。事務的な問い合わせや他の相談機関への取り次ぎだけでなく、心理的な問題への介入も行うようになりました。
「総合窓口」では、これまでに拾いきれていなかったニーズに対応することを目指しています。例えば、「どこに行ったらいいかわからない」「メンタルヘルスについて相談しにくい」という方がまだまだいます。深刻なものでは、外部とのつながりもなく「命を絶ってしまいたい」という方で、保健センターで手詰まりになっているケースを依頼されることもあります。そうしたことも含め、専門的にいろいろなことを取り扱う、という意味で「総合窓口」という名前になりました。
——総合窓口にはどのような相談員がいらっしゃいますか。
学内の保健センターから移ってきた人もいれば、地方の大学や海外で働いていた人もいたりと、様々なバックグラウンドを持つ専門家が集まっています。このようなバラエティ豊かなメンバーが2人3人で対応することで、多様性のある悩みや症状に幅広く応じられる態勢を整えています。
性格に関しては、相談が好きで、積極的に相談に応じたがるような人ばかりですね。
——1回で終わるケースでも、最初から複数人で対応するのですね。
そうですね。相談内容に応じて誰が適任か考え、日程調整しています。例えば、医療的な見立てが必要であれば医師や心理士が入り、福祉的なものであれば精神保健福祉士が入ります。ただ、複数回お話を聞いていくうちに様々な悩みが出てくることもあるので、メンバーは固定ではなく、時には全員で連携することもあります。学生相談所では1対1のカウンセリングを行っているので、そこは違いなのではないでしょうか。もちろん一人で対応してほしいという場合等では、臨機応変に対応しています。
また、週一回カンファレンスがあり、情報は部署内で共有されています。そこで、改善策などを率直に話し合うようにしています。
——相談内容としてはどのようなものが多いですか。
メンタルヘルス不調が多い印象です。また、「教授とうまくいかない」といった人間関係の相談や、「卒業が難しい」といった進路の悩みもよくあります。
「論文・研究が進まない」と提出締切前に来所されるケースもあります。その場合は、原因を一緒に考えたり、教授とのミーティングの場を設けたり、休みが必要であれば、保健センターを紹介して診断書を書いてもらったりします。
学部や研究科にも相談機関がありますが、両方に相談しているケースや、お互いを紹介するケースなどもあります。
フォームの申し込みも、2年くらい前からどんどん増えています。どこに相談していいのか、どういう相談施設があるのか、知らない方もまだたくさんいるようです。
——コロナ禍で相談内容に変化はありましたか。
コロナ禍で楽になったという人も、逆に辛くなったという人も両方いるようです。ひとり暮らしを楽しむ人もいれば、寂しさが増したという人もおり、「レポートがこれで良いのかわからない」という悩む声もありました。以前のような日常が戻るにつれ、通学が辛い、というような相談も多くなりました。
——英語に加えて中国語での相談も受け付けていますが、留学生からの相談も多いのですか。
そうですね、特に中国語での相談が多いです。留学生支援室でも、特にメンタル支援などはやっていると思いますが、ちょっとした相談事とかだと総合窓口のほうが来やすいのかもしれないですね。「総合窓口」だからなんでもいいんだ、と思うのでしょうね。あとは教員からの英語での相談も多いです。
現在総合窓口は心理士の中に英語と中国語、それぞれ1人ずつ対応可能な相談員がいます。
——教職員や保護者からは、それぞれどのような相談が多いですか。
教職員の場合は労務問題や人間関係など、様々な相談があります。雇用問題については、社会保険労務士の資格を持っている相談員もいるため、助言できることもあります。相談件数は増えているのですが、多くの相談機関は学生を対象としており、教職員からの相談を受け付けている相談機関はほとんどないのが現状です。
保護者の場合は、子どもへの対応の仕方に関する相談が多い印象です。例えば「子どもが大学に行かなくて困っている」といった相談があります。
——予約なしの相談も受け付けているとのことですが、その場合、どれくらいの待ち時間で相談できるのでしょうか。
受付に来てもらって、相談員が空いていればすぐ相談できるため、基本的に待ち時間はないと思います。予約ありの場合と比べ複数人での対応ができないなどの違いはありますが、今すぐ話したいという場合にも相談員の空きがあれば対応するようにしています。
夏休みなどの休み期間は件数が減ります。逆に論文や課題、試験の前や学園祭の季節などは増えます。
——相談だけでなく、認知行動療法などのワークショップも開催されていますが、どのような狙いや思いで行っているのですか。
認知行動療法ワークショップは3年ほど前から始め、学生や教職員を対象に実施しています。
当初は、学生相談所などの他の部署の先生方と一緒に何かをやろうという流れで研究ベースのワークショップを始めました。「最近ストレスたまってるな」程度に感じているような方々がより具合が悪くならないようにするための予防策という位置づけで実施しています。
——ワークショップなどの相談以外の取り組みは今後も予定していますか。
今回の開催により、学内に相談できる機関が少ない教職員にもストレスマネジメントのニーズがあることが分かったので、教職員も学生も対象に含めて続けていきたいと考えています。また、他の療法によるワークショップや、研究ベースではない単発のワークショップも検討していきたいです。
——広報はどのように行っていますか。その中で何か感じていることはありますか。
ポスターは掲示できるところには沢山出すようにしています。できることは色々しているのですが、知らないので来られていない人もまだ多いと感じているので、もっと周知が必要だと思います。ワークショップの最後のアンケートには、「こういうワークショップがあったんですね」というご意見が多くあります。
——今後目指している相談のあり方などはありますか。
現在は周知をおこなってたくさん人が来てくれるようにしているところですが、今後は相談対応の質を上げていきたいと考えています。
1回来て終わってしまう方に対して、「1回で何を伝えられるんだろう」「何か相談に来てよかったと思えるような“お土産”を持ち帰っていただきたい」と常に自問しています。
個人的には、相談支援研究開発センター全体として(守秘義務に抵触しない範囲で)もっと機関を越えた有機的な横の繋がりを強めていきたいと考えています。現在はそれぞれの部署の内部が見えづらい状態になってしまっているので、ワークショップも、センター全体で行うイベントという位置づけでやりたいです。
——最後に、相談機関に行くことにためらいを感じている学生に向けて、何かメッセージをもらえますか。
「こういうことで相談していいんですか」という方もいるのですが、本当に何でもいいんです。話に来るだけでも大歓迎です。一人で悩みを抱えることはつらいので、気軽に来られる場所として知っていてもらえると嬉しいです。
——ありがとうございました。
【インタビュアーを終えて】
様々な悩みを抱える学生に対し、総合的に、かつそれぞれの悩みに寄り添った相談対応をされているところが印象に残りました。また、少し遠い存在に感じていた相談というものをとても身近に感じました。生きてるとどうしても、しんどいなと感じるときはあると思います。つらいよって方も、少し悩みやもやもやを抱えているよって方も、家族や友達に相談するのと同じように、一度総合窓口を訪れてみてはいかがでしょうか。
インタビュー日時:2024年3月12日
※本文中の用語・制度・法令・資格等はインタビュー時点のものです。